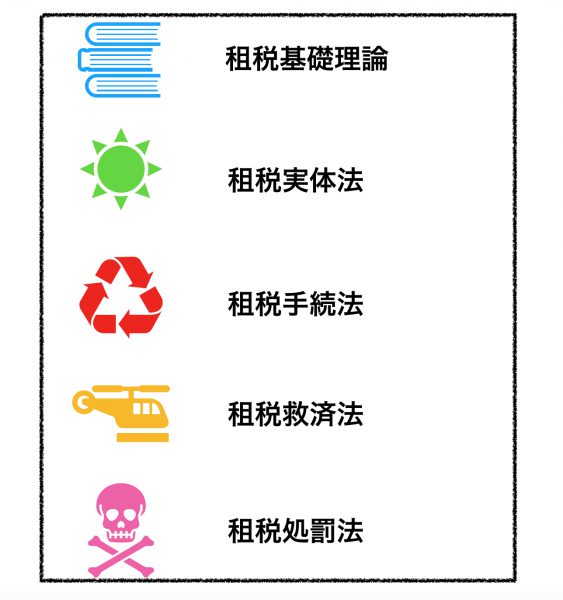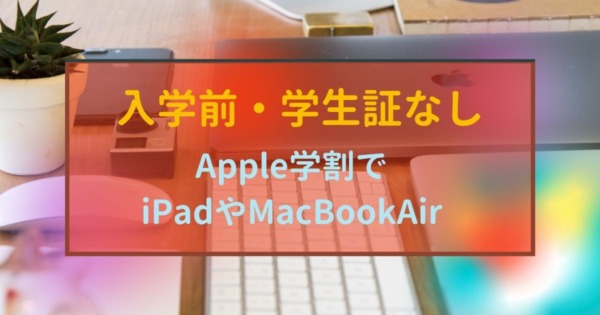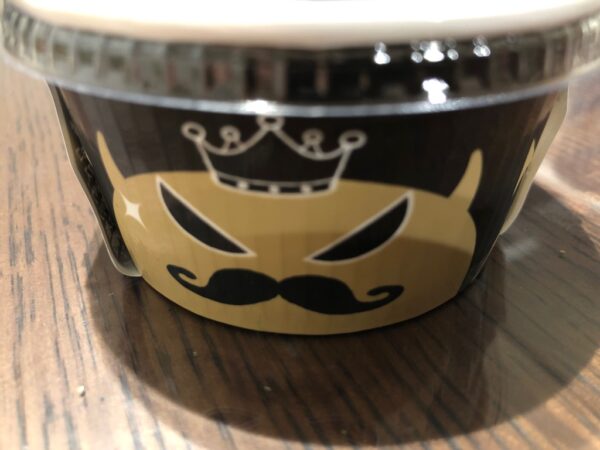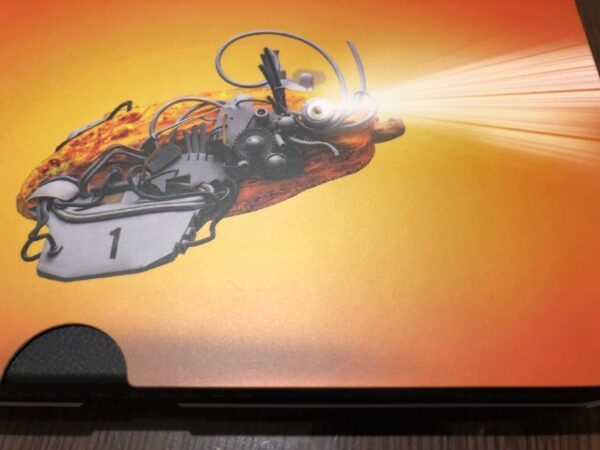2019年2月– date –
-

国にとって租税条約を結ぶのは得なのか?租税条約モデルと租税条約解釈
租税条約を結ぶ理由、租税条約のモデルと解釈について考えていきます。 租税条約は国にとって得なのか損なのか 租税条約が結ばれていますが、なぜ結ばれているのでしょうか。 主要な目的は二つ挙げられます。 二重課税の回避 一つは二重課税... -

納税国は住所地がある国なのか、源泉地のある国なのか
2つ以上の国が絡む税金の徴収において、問題になるのはどこの国に税金を納めるかです。 管轄(jurisdiction)を決めるというところですが、税金を納める人が住んでいる国で納めるという考え方と、所得が発生する国で納税するという考え方があります。 国によ... -

二年目に入った毎日更新「ブログの収益」と「軸作り」を振り返る
ブログからの収益はどれくらい何が稼げるのかの点を少し振り返ってみます。 稼ぎは金銭換算できるものをもちろん出しますが、自分の軸づくりという目線でも書きます。会社勤めをしながらだとマーケット感覚が正常に保たれているか。 正しい軸作りができて... -

税金は法律で定められた通りに徴収されること、公平であること(租税法律主義と公平負担の原則)
税金が課される際に大切な概念として、租税法律主義と公平負担の原則があります。 言われたら当然ではあるのですが、法律に従って徴税されることと、公平に負担させるという二つの概念。 話を進めていくほどに大切になるため、基礎の大切な理論です。 今回... -

過度な節税は脱税なのか? 節税・租税回避・脱税の言葉の定義
エコノミスト(2018.1.30.P27)には、こんな記述がありました。 ・・・税理士側も、過度な節税は「脱税」という認識を示したとみられる。 (下線部はAK-UP.COMで付加) 「過度な節税」=「脱税」なのでしょうか。 例えば、法人が保険により1... -

租税法の5つの体系と租税法を構成する法律
今回は租税の体系についてです。 租税を学ぶ際には5つに分けていくことで全体を把握しやすいです。 税法の体系 租税法を構成する法はたくさんあります。 その複雑な体系を理解する構成を考える上で、以下の5つに分けて議論することが多いです。 &nb... -

入学前・学生証なし、Apple学割でiPadやMacBookAirを学割で購入する
大学や大学院の学生になったら、Apple製品を学割で買おうと考えていると待ち遠しいですよね。 実は、大学への入学を待たずともすでにAppleの学割で商品を購入できます。入学前に買うとバレるのでしょうか? いえ、実は学生証がなくても合格していれば、学... -

国際租税法入門:税金はどの日本で課税するべきか。所得税・法人税の納税義務者と関連法令
国際租税法についてもまとめを進めていきます。 まず、税金はその地域や国で課されています。 租税法を考える際は、その地域、つまりは日本を中心に論が進んでいきます。 国際租税法は、日本以外の地域や国での課税、及び日本の租税との関係を考える領域で... -

がん保険を選ぶ際にオプション選択で考えるべき3+1の要点
がん保険に入った方がいいのかどうか。迷うところです。 入るにしてもどの辺りが検討材料なのか。 個別に設定できるオプションがとにかく多いです。 大まかにでもオプションの検討方向性を知っているだけで選択肢が分かりやすくなります。 選ぶ要点をま... -

営業だけがうまい士業は非難されるべきか。サービスとサービスの利用コストを考える
「実力がないけど営業が上手な士業が、実力はあるけど営業が下手な士業から仕事を奪っている」という趣旨の話を目にしました。 この内容を発した人は「正当に積み上げた能力が評価されるべき」ということを言いたかったのかと考えております。 実力に比... -

名前は租税法か税法か?租税法を学ぶ目的は?租税の性質は?
弁護士、公認会計士、税理士共に、租税法が関係していきます。 体系的な知識を身に着けるために、この租税法を少しずつ自分なりにまとめていきます。 まずは租税とは何かというところから始めていきましょう。 税法と租税はどちらを使うべき... -

「租税法入門」の参考書籍ページ
租税法の学びの際の参考書籍一覧のページです。 税法免除免除大学院のため入門書の一覧はこちらにもまとめております。 税法免除大学院希望者向け、研究計画書を作るための租税法入門書 1. 税法入門 金子宏ほか 金子宏先生が...