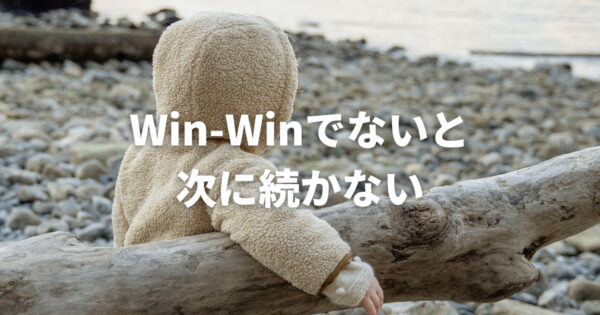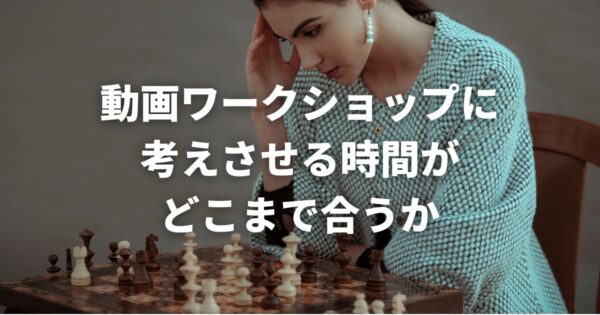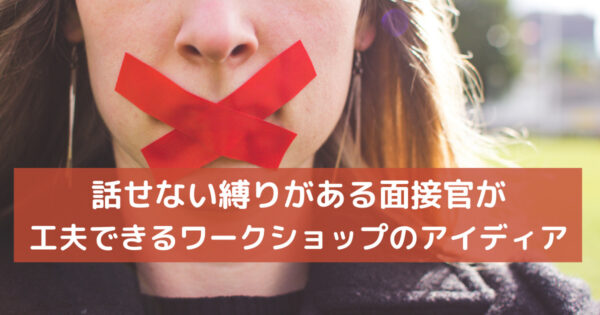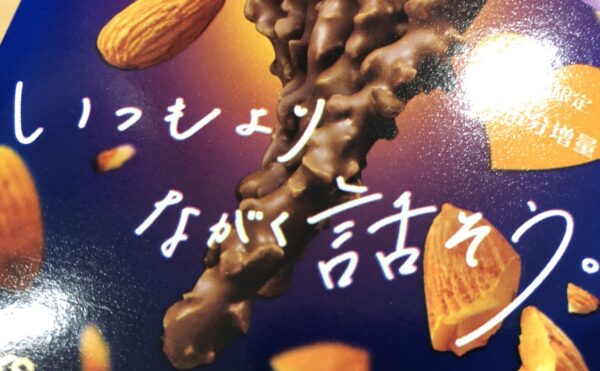理論・実践ワークショップ– category –
-

ビジネス系でワークショプがあまり流行らない理由
ワークショップは一時期流行っていましたが、今は、基本的な事項に落ち着いた感じがします。取り組む分野によっては当たり前になっていますが、全く浸透しない場合もあります。ビジネス系でワークショップが流行らない理由をまとめてみます。 上下を平らに... -

ワークショップの要約とAI要約から、役割分けを考える
ワークショップの要約と AI の要約の違いに興味がありますか?ドキュメントを要約する際に、それぞれがどのような役割を果たしているのか、同じようで異なります。両方のタイプの要約から役割の分割を調べ、それぞれを効果的に使用する方法についての洞察を... -

チェックインとオンライン会議
オンライン会議は最近当然のごとくあります。便利だということがひとつ。 遠方であっても、複数のグループであっても時間をつくりやすいです。それによって成果物を早く仕上げられます。 一方で、チェックインと呼ばれる話し合いの最初の部分がイマイチと... -

Win-Winでないと、次に続かない
Win-Winは、交渉事でよくある形。交渉をまとめるために言われることが多いです。 でも、本質はそれだけでなく、次につなげるために必要ということです。 いい過程があるか いい交渉でなければ、その結果のビジネスでなければ次につながりません。 交渉は、... -

動画ワークショップに考えさせる時間がどこまで合うか
ワークショップを動画でしたいという欲求はそこそこあります。現状は、その理論をしっかりわかっている人たちでないと難しいですが。 でも、この欲求はどこから来るのでしょう。それは、考えてもらいたいという発想からです。 考えて、腑に落ちる状態にな... -

ファシリテーターの「感じ取る力」「表現による固定化」「感じても流す力」
相手であったり場の雰囲気をよく感じる力というのは、役に立ちます。特にファシリテーターは。後天的にも身につけられるのでしょうが、気質のようなものもかなり反映されているのかなと。 ただ、感じ取った上で具現化するから、言葉にするからその認識が共... -

ワークショップ ファシリテータのモチベーションがどこにあるか、7つ
ワークショップのファシリテータのモチベーションはどこにあるでしょう? ファシリテーター自身も自己原因性を持って取り組むことがよいファシリテーターになる方法と感じます。ただ、いろいろな依頼のされ方もありますし、いつもいつもモチベーションを保... -

発言ができない面接でワークショップデザイナーが意識している8つのこと
あまり発言ができない面接があります。主体として出る人が他にいるものです。 発言しない場合には、その会議に出る意味はない などとも言われますが、ワークショップを学んだ立場として、発言がほとんどできない縛りがある上で、どう役立つか。 8つの点で... -

わかり合うことを求めるのか、結論を決めるのか
お互いが気持ちも含めて完全にわかり合うまで話し合わなければ結論がでないと考えるやり方があります。 一方で、完全にわかり合うことまで行うことは不可能と理解し、論点や歩み寄れる部分のすり合わせを中心に行う考え方があります。 前者は同意形成と呼... -

セミナーやアクティブラーニングに使えるオンラインのワークショップの6つのコツ
ビデオでの会議やセミナーなどが増えるに従って、 その使い方に幅が出てきています。 大学の授業でも使われることで 双方向の内容に仕上げていっていることも見かけます。 伝統的な一方向型以外でも やり方によってオンラインでも対応できる いい例です。 ... -

「結論よりも過程が大切?」ファシリテーションの立場から
ムダな会議はするな。 そもそも会議はするな。 効率的にものごとを運べ。 など。 ただ、よいチームを作ることが結果的にその結論の質を上げることにもつながる。 こういう考えはファシリテーションの底の方にあります。 人が流動的でない場合は、チーム作... -

弁護士等が素人への法律ワークショップで気をつけるべきポイント3点
弁護士や社労士など、法律の専門家にワークショップを行ってもらおうという団体からや教育関係者のセッティングを見かめます。 やはり本場から行ってほしいという現場のニーズと、当該団体が活躍の場を増やしたい考えがあるためでしょう。 専門的に学んで...